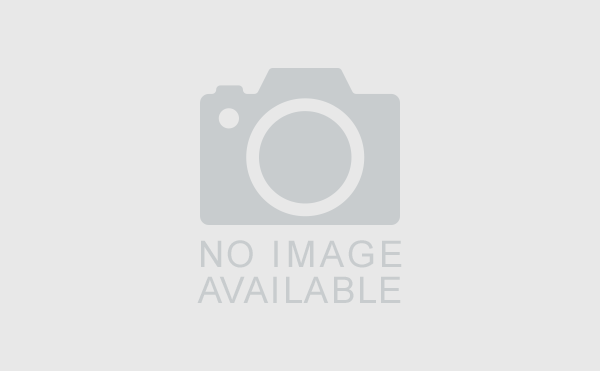会派代表質問二次 2月28日
下記は、2月28日に行なった会派代表質問の2次質問の原稿です。各質問とも、私の一次質問に対する当局の答弁を前置きとして要約しつつ、質問に入っているので、一次質問に対する当局の答弁はご理解いただけると思います。二次質問に対する当局の答弁は、一次質問に対する答弁と大きく異なるものではないとご理解下さい。なお、さらに関心のある方は、市議会のホームページで、議会のネット中継録画をご覧下さい。
1.施政方針について
(1)まず、施政方針そのものについての質問ですが、「施政方針はバラ色の夢を語るだけでなく、もっと市政の重要課題について、取り上げるべきではないか」と私は質問をいたしました。これに対して、「施政方針は、基本的な課題や施策を説明するために、新規、拡充事業を中心に、翌年度の重要事業について申し挙げている」との答弁をいただきました。たしかにそれはその通りだと思いますが、その結果として、施政方針ではバラ色の夢ばかりが多く語られ、その裏側にある市政の重要課題にフタをしてしまって、何らの解決方針も、市長のこれらの問題に取り組む決意も語られないままに終わっているように思います。私は、これでは施政方針は単なる政治的なプロパガンダであって、市民に対する欺瞞にすぎないように感じられますが、これは意見にとどめさせていただきます。(意見のみ)
(2)施政方針がどのように作成され、市長はどのように関わったのか、という私の質問に対しては、「宝塚という街を、市民とともに築き、未来につなげて参りたいとの思いを込めて、市長自身が素案の作成から最終原稿の確認まで関与している」との答弁をいただきました。そうであるならば、市政運営の基本方針における3つのスローガンには、市長の思いが強くこめられていると思います。そこでおたずねしたいのですが、特に「人権、いのちと暮らしを未来につなぐ」というスローガンの意味がわかりにくいと感じますので、市長の思いがどのようにこめられているのか、ご説明願います。
2.施政方針は誰に向けられたものか
(1)施政方針において、施政の重点はいかなる市民層に置かれているのか、という私の質問には、「全ての市民にとって魅力ある街作りを進める」という、当たり前のような答弁をいただきました。しかし、市政は全ての市民に対して行なわれるべきであるとしても、ときの市長によってその重点のおきどころは異なると思います。たとえば、一次質問でも申し上げましたが、前の中川市長は、「政治は生活に困っている人のためにおこなうもの」と述べられていたものと記憶いたします。そのような意味で、山﨑市長にも施政の重点の置き所はあると思うのですが、いかがでしょうか。
(2)施政方針において、サラリーマンに対する施策は何があるか、という質問に対しては、「会社員といってもさまざまであって、会社員という区分による一律の施策を示すことができない」との答弁をいただきました。たしかにその通りだと思います。そこでサラリーマンの範囲をもう少し絞りまして、毎朝電車に乗って大阪や神戸の会社に出かけ、日中はずっと会社で働いていて、宝塚には夜遅く寝に帰ってくるだけ、とい会社員を想定してみたいと思います。この人達は、仕事が忙しくて市の政治に対する関心が低いということもありますが、市議会でもこの人達の立場で意見を述べる議員はいないと思います。いわば市の政治において取り残されがちな多数派の市民ということができると思いますが、この人達に対する施策は何があるでしょうか。
○次に、サラリーマンというコトバの問題ですけれども、「男女共同参画の視点に立ったガイドラインに従い、会社員という表現を使わせていただく」との説明がありました。しかし、会社員というコトバには、単に民間企業の従業員という冷たい意味しかなく、それに対して、サラリーマンというコトバには、元々は月給取りという意味に過ぎなかったものが、長い歴史の中で、さまざまなニュアンスをこめて使われるようになった重要なコトバであると思います。この重要なコトバを、一部の市民からの批判を避けようとして排除するようなマゴコロのない姿勢が、行政のサラリーマン軽視、無視につながっていると思いますが、これも意見のみにとどめます。(意見のみ)
3.財政について
(1)財政は「依然として厳しい」というよりも「今後ますます厳しいものとなる」と認識すべきではないかとの私の意見には、概ね同意されるものと理解いたします。(意見のみ)
(2-1)「規律に基づく財政運営」について、「令和3年度に策定された財政規律に従って財政運営を行なっており、来年度の当初予算についても、この財政規律に従って予算作成を行なった」との説明がなされました。その中で、財政調整基金についての説明がわかりにくかったのですが、当初予算では19.8億円も取り崩すことになっているために、「標準財政規模の10%を維持すべし」とする財政規律を守ることができず、3月の補正予算になって、取り崩し額を減額することで標準財政規模の10%を維持できるのだと、私は理解いたしました。要するに、予算の上で、たとえ一時的であるにせよ、本市は自ら策定した財政規律を守ることができなかった・・・と、このように理解したのですが、よろしいでしょうか。
(2-2)財政調整基金の積み立て目標額は自治体によって異なり、その適正規模は標準財政規模の10~20%であるといわれております。本市のお隣の伊丹市では、標準財政規模の20%を目標として、その目標を、余裕を以てクリアしているようですが、本市はその半分の10%と自ら定めた目標も達成することができない(達成することに苦労している)・・・これでは本市の財政運営は、伊丹市と比べて非常に心許ない状況にあると思いますが、いかがでしょうか。
4.市立病院について
(1)令和5年度の病院事業会計予算における、入院単価70,000円の設定は、宝塚市立病院が目指す病院像における目標が早くも変更を余儀なくされたということか、という私の質問に対しては、「昨年からの良好な病院経営を反映した上方への修正であって、下方修正を余儀なくされたものではない」との主旨の答弁であったと理解致します。経営改善の取り組みによって、入院患者の入院期間を短縮し、DPC(1+2)の入院患者の比率を高めたことが増収につながったということですが、そのためには、市立病院を退院していただいた回復期の患者を受け入れる近隣の病院との地域連携が不可欠だと思います。そのような、いわば協力病院との連携は十分に進んでいるのでしょうか。
(2)地方独立行政法人への移行は検討もしていない、という姿勢は今も変わりはないのか、との私の質問に対して、地方独立行政法人化することのメリットはそれほど大きいものではなく、デメリットもあることから、公営企業法全部適用の公立病院に踏みとどまることに決定した、という主旨の答弁がされたものと理解いたします。地方独立行政法人化することのメリットとデメリットについて、簡単明瞭にご説明願えますか。
(3)病院の建て替えについて、どのような検討がなされているのか、との私の質問に対しては、「未だ全然何も決まっていない、病院を建て換えてそれを開院までに今から少なくとも7年はかかる」という主旨の答弁がなされたものと理解いたします。これは、宝塚市立病院とほぼ同時期に開設された箕面市立病院や伊丹市立病院が、立て替えの場所や新たな病院の経営形態まで決まっているのと比べて、あまりにもおそいと思います。過去のことを振り返ってもしかたがないと思いますが、箕面市立病院や伊丹市立病院と比べて何が悪かったのか、市のトップの判断に問題がなかったのか、ということも含めてご説明をお願い致します。
5.魅力ある街作りについて
(1)「文化の自己決定能力」とは何か、それが街作りのために、どのような意味で重要なのか、との私の質問に対して、一応の答弁はいただきましたが、その意味が依然としてよく理解できませんでした。「文化の自己決定能力」とは何か、どのような意味で重要なのか、恐縮ですが、わかりやすくご説明願います。
(2)一民間企業のビジネスにすぎない宝塚歌劇や、一個人の著作物である鉄腕アトムなどに本市のイメージアップを依存しすぎること、またモダンアートの作品を公共施設に設置することは好ましいことではなく、抑制するべきではないかとの私の質問に対して、「宝塚歌劇や手塚作品は、観光客の皆様など、すべての方に対して誇れる本市の貴重な財産であり、またモダンアートについても本市ゆかりの芸術家の作品を公共施設に設置することはシビックプライドの醸成に寄与する」との答弁をいただきました。私もそういうことを否定するつもりはありません。宝塚歌劇や手塚作品、モダンアートの大いなる価値は認めます。しかし、過度にそれらに依存することについて何の問題もないのか、リスクはないのか、とお尋ねしております。当局の認識をお聞かせ下さい。
(3)「かつてのニュータウンであるところの山の手の住宅地が今やオールドタウンと化し、空き家が激増しつつあることについて、どのように対処すべきであるか」との私の質問に対しては、「空き家対策の推進に関する特別措置法に基づく施策や、官民の協働による、空き家等市場流通促進のためのセミナーなどを開催した」との答弁をいただきました。当局の施策は既にできてしまった空き家をどうするか、という施策であって、それはそれで大切なことだと思います。しかし、その前段階の、空き家の発生を防ぐための施策も検討するべきだと考えます。今、山の手の住宅地を歩いてみると、すさまじい勢いで空き家が増えており、また、今はまだ空き家でなくとも、老人のひとり住まいとなっているお宅も多数見かけられます。そのような地域では、街がさびれているというだけでなく、商業施設や交通機関も衰退し、住宅地としての環境が悪化しています。これは、単なる空き家対策でなく、住民の住宅地としての居住環境をどう守かという問題になりますが、この問題に対する当局の認識をお聞かせください。
6.学校教育について
(1)一次質問で私は、私は、旧来の画一的授業をやめ、児童・生徒の個性や学ぶ意欲、学習到達度に応じられるように、授業のやり方や学校のあり方も改革していくべきだと意見を述べ、これに対する教育委員会の認識をお尋ねしました。これに対して、教育長は、「主体的で深い学びを実現するために、少人数教育やICTを活用した授業に取り組んでいる」との答弁をされました。しかし、その少人数教育なるものは、児童・生徒の個性や学ぶ意欲、学習到達度に応じるものでなければ、いくら少人数教育となっても、旧来の画一的授業と何ら異ならないと思います。例えば体育の授業では、跳び箱を三段しか飛べない児童に六段を飛ばせることはムリであり、六段を飛べる生徒に三段を飛ばせるのがムダであることは明らかです。しかし、国語や算数などの教科の授業では、明治の時代から合いもかわらず、ムリヤリ全員に同じことを教えようとしている。もうそろそろ、全員一斉の画一的授業をやめ、児童・生徒の個性や学ぶ意欲、学習到達度に応じられるように、授業のやり方や学校のあり方も改革していくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○できない子どもにできるようにしてやることが大切・・との説明がありましたが、それはあたり前のことで、それこそ教育のイチバン重要な目的だと思います。そのためにも私は、個性や学ぶ意欲、学習到達度に応じられるように、授業のやり方や学校のあり方の改革が必要であると考えます。
○ただ今のご説明には、ほとんど授業のやり方や、学校のあり方を改革する必要性について、ほとんど理解がなく、明治以来の画一的な教育にしがみつこうとする姿勢のように感じられますが、次の質問にうつります。
(2)一次質問で私は、ご家庭が子どもを学校外の学習塾などへ通わせることについては、学校教育とは何ら関わりのない問題であるとして、相変わらず無視するのか、との質問を致しました。このような質問をした理由は、一昨年の一般質問で私が、「小中学校では学習塾などに通塾している児童生徒を把握して、何らかの対応をいるのか」と質問をしたときに、当時の学校教育部長が、「ご家庭が子どもを学習塾などに通わせるのはご家庭が自由にされることであって、学校ではそのようなことは一切把握していない」と答弁されたことにあります。これではまるで公教育の学校だけが正規の教育機関であって、学習塾などは正規の教育機関とは認めない、といっているように聞こえました。私は、今日では公教育の学校側のこのような唯我独尊的な態度は許されないと考えます。今日ではむしろ、公教育の学校よりも、むしろ、学習塾をはじめ、公教育の外側で行なわれるさまざま教育の果す役割がますます大きくなってきていると考えます。公教育の側では、公教育以外の教育機関の果す役割を認知し、それらとともに教育を担う姿勢が必要であると、私は考えますがいかがでしょうか。
○教育委員会には、未だに学習塾のような公教育の外にある教育機関に対してどのように向き合っていくべきかについて、未だ何の方針もない様に重いますが、これは考えて見ればあたり前のことのようにも思います。今、東大を出た文部省の役人100人に、小学生や中学生のときに学習塾に行っていたかと尋ねたら、100人が100人とも行っていたと答えると思います。学校と塾と、どっちの勉強が大事やった?と聞いたら、立場上答えられないと思いますが、それは塾に決まっていると思います。その文部省が、学習塾を教育機関としてまともに認知しようとしていない・・。私自身は、実は、学習塾からワタクシリツの受験名門校へ進学するコースの存在が、さまざまな意味で日本の教育を大きくゆがめていると思っているのですが、非常にむつかしい問題なので、これについての質問は差し控えます。(意見のみ)
(3-1)教育委員会の委員の選任の仕方も含めて、教育委員会を活性化する方法を検討するべきではないかとの質問に対しては、「教育長・教育委員と市民の懇親の場を開催したり、教育委員の学校訪問を実施してその活性化を図ってきた」との答弁をいただきました。しかし、その程度の小手先のことでは、私は、教育委員会の活性化は到底実現しないと思います。教育委員会の議事録を見て痛切に思うことは、事務局の説明ばかりで、委員からの発言はほとんどないことです。教育については、誰しも自分自身が教育を受けた経験があり、また多くの人が親として子どもに教育を受けさせる中で、悩んだり、ご苦労された経験がおありだと思います。中にはおおやけの場で、自分の意見を積極的に述べたいと思っている人も少なくないはずで、そういう方に教育委員に就任していただくことが望ましいと考えますがいかがでしょうか。
(3-2)教育委員の選考にあたっては、市長や教育長も加わり、多くの職員がかかわっているとも聞きました。しかしその選考過程は、まったくのブラックボックスであって、私のような議員にとってもナゾに包まれています。私は教育委員の選任を公募制にしてオープンにすることが望ましいと考えますが、いかがでしょうか。
○かつて一時期、本市でも教育委員の選任が公募制であったと聞きましたが、それはなぜヤメルことになったのでしょうか。市長が「あなたにオープン」といって登場された市長なのに、なぜ何でももっとオープンにしようという姿勢がないのか・・非常に残念です。
7.市民の安全の確保について
(1)一次質問では、外国との戦争が現実におきてしまったときの市民の安全確保について、市は、戦争がおこらないことをバクゼンと期待するだけでよいのか、との質問をいたしました。外交や国防は、国の問題であって、市議会で質問をするようなことではないと思われた方が多いと思いますが、市民の生命の安全を守ることは、市の責任であって、今戦争の危機が国際的に高まっている中で、戦争が起きてしまったときに、市民の安全をどのように守るべきかは、喫緊の課題であると思います。答弁では、「Jアラートと連携した防災行政無線やメールなどを運用し、避難施設を指定している」という説明がありましたが、さらにしっかりと検討を続けていただきたいと思います。(意見のみ)
(2)次にエネルギーの問題について、市民のイノチを守るために必要であるとの見地から、将来の電力をはじめとするエネルギーの確保が懸念される中で、市は、エネルギーの確保について、市とはかかわりのない問題であるとして傍観しているだけでよいのか、との質問をいたしました。これに対して、「本市においては、再生可能エネルギーの利用を推進し、エネルギーの自立性が高い持続可能なまちづくりに取り組んでいる」との答弁をいただきました。非常に前向きな答弁だと思いますが、エネルギーの自立性が高い持続可能なまちとは、一体どのような町かご説明をお願いいたします。
○ありがとうございました。以上で2次質問を終わります。(終わり)