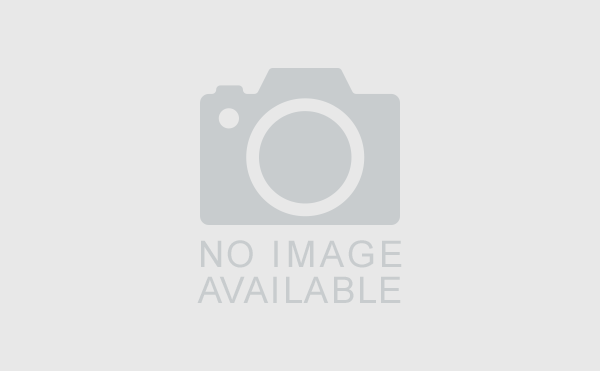会派代表質問 2月28日
1.施政方針について
無所属の会 田中大志朗でございます。はじめに、市長によって示された施政方針そのものについて質問をさせていただきます。
まず、施政方針の全体から受ける印象ですが、あまりにもバラ色の夢ばかりが多く語られているという印象を受けます。宝塚には深刻で急を要する課題がたくさんあるはずですが、最も重要な課題である財政の再建や市立病院の問題でさえも、ごくわずかの行数でしか語られていません。施政方針は、政治的なプロパガンダではなく、これから1年間の市政の重要課題を見渡し、そして見つめるための文書であると思います。施政方針はバラ色の夢を語るだけでなく、市政の重要課題について、もっと丁寧に取り上げることが必要であると思いますが、いかがでしょうか。
次に感じたことは、第2章で示された「市政運営の基本方針」が、3つの柱につけられた長ったらしいスローガンのような標題のせいで、却ってわかりにくくなっているということです。「市政運営の基本方針」はもっとシンプルに、「子育て環境と教育の充実、人権の尊重と福祉の向上、魅力ある街づくりの3つである」というように、わかりやすく、そして言いやすく表現するべきだと思います。
続く第3章では、せいぜい5~6行ていどに短くまとめられた個別の施策が、ばらばらに並んでいるような印象を受けます。これはおそらく、行政を担うすべてのセクションがそれぞれの担当分野を分担執筆し、それをつなぎあわせた結果であろうと想像します。そして第2章の「市政運営の基本方針」がわかりにくいのは、先にできた第3章をもとにしてあとからムリヤリまとめらたからではないか、3つのスローガンは、その段階で市長から示されたものかもしれない・・・私はこのように想像しました。施政方針の作成も大勢の職員が関わる重要な行政の一環であると思いますので、それが一体どのように作成されたものであるのか、特に市長はどのように関わったのか、そのプロセスをオープンにして説明をしていただきたいと思います。
2.施政方針は誰に向けられたものか
続きまして、この施政方針が一体誰に向けて述べられたものか、を問題にしたいと思います。すなわち、市長や行政は誰のために仕事をしようとしているか、ということでありますが、その答えはもちろん「市民全体のため」に決まっています。しかし、それは形式的な答えであって、現実には、施政の重点のおきどころは、ときの市長の政策や主義.・主張、いかなる市民に支持を受けて当選されたかによっても大きく異なってくると思います。たとえば、前の中川市長は、「政治の目的は、生活に困っている人を助けること」と述べておられましたが、これがもし保守派の市長なら、施政の重点は、会社経営者や裕福な人達に置かれるのかもわかりません。そしてそれはおのずから施政方針にも反映されてくるものと思います。
そういう意味での施政の重点は、いかなる市民層におかれているのか。施政方針に示された文言から推察をするかぎり、第一に子どもや子育て世代、第二に高齢者や障害者、そして第三に商工業などの自営業者や農業従事者であろうと思います。しかし、これで市民のすべてが尽くされているか、といえば、私には一番数が多い重要な存在、すなわちサラリーマンがすっぽり抜け落ちていると思います。子ども達が安心して穏やかに育つ町を「つくる」ということが、市政運営の基本方針の1つである以上、子どもの親としてのサラリーマンにも一定の施策が為されることは理解できます。しかし、私はもっと明確なサラリーマンに対する施策が必要であると思います。
私には議員となる前、長いサラリーマンの経験がありまして、独身時代も長く、正直に言えば、高い税金を払っているのに行政は何もしてくれない、と言う不満がありました。今、議員となってみて、やはりサラリーマンからの政治に対する、そのような不満や不信感を強く感じております。そして、それが市政に対する無関心と、選挙における投票率の低さにつながっているのだと思います。施政方針において、サラリーマンに対する施政は何があるのか、ご説明を求めます。
3.財政について
次に財政について質問をいたします。施政方針の中では、わずかに1ページの半分程度でしか語れられていませんが、持続可能な街作りを進め、宝塚の未来へとつないでいくためには、避けて通ることができない最も重要な問題であると考えます。
まず本市の財政に対する認識として、「依然として厳しい状況にある」と述べられています。この書き方から察するに、財政当局は、世の中の物価高騰が収まるとか、景気が回復するなどの外部要因の好転によって、財政の厳しさはやがて回復すると考えているようですが、この認識は大変あまいと思います。本市に限りませんが財政悪化の原因は、民生費の極端な膨張であり、その根本の原因は少子高齢化です。少子高齢化の問題には、今国をあげて取り組もうとしていますが、国民の生き方の問題であって、児童手当を増額したぐらいのことでは解決できない問題であると、多くの人が考えています。従って、財政は「依然として厳しい」ではなく、「今後ますます厳しくなる」と認識すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
次に財政健全化のための方策として、「規律に基づく財政運営に勤め、成果の視点に立った事業の見直し」を進めると書かれていますが、具体的にはどのような財政運営を進められるのでしょうか。ある新聞(神戸新聞)によれば、本市の新年度予算について「一般会計は4年連続で最高を更新する一方、財政調整基金からは直近10年で最大となる19億8千万円を取り崩すキビシイやりくりとなった」と報じられています。この新聞を読むかぎり、本市では、規律に基づく財政運営など全然実行されていないように感じられます。また、施政報告第4章の予算規模の説明では、「当初予算案は・・・合計で1725億円となった」と説明されています。これではいかにも自分が決めたのではない、出せといわれたオカネを全部出したらこんな金額になりました、というように聞こえて、規律に基づく財政運営に務めようという意志あまり感じられません。財政当局には財政規律を堅持する意思が本当にあるのかと疑いたくなりますが、いかがでしょうか。
4.市立病院について
市立病院についても施政方針ではわずかに5行程度が記されたのみですが、結論の先延ばしは許されない緊急を要する問題として質問をさせていただきます。
まず経営強化策ですが、宝塚市立病院が目指す病院像では、入院単価65,000円、1日あたりの入院患者数340人の目標を設定し、それを維持することで黒字継続を目指すとの説明がされていました。私は昨年の一般質問で、それが実現できる根拠に乏しいとして批判したところですが、新年度の病院事業会計予算によれば、入院単価は70,000円、入院患者数は315人と、異なる設定がされています。これは宝塚市立病院が目指す病院像で設定された目標が早くも変更を余儀なくされたということでありましょうか。また、入院単価を70,000円と設定した根拠をご説明願います。
次に、経営形態の見直しについて。公立病院を地方独立行政法人に移行させることが、総務省の示すガイドラインの推奨するところだと私は理解していますが、昨年9月の私の一般質問に対して、「借入金がある段階では地方独立行政法人への移行は認められないので、検討もしていない」との説明がなされました。しかし、このような経営姿勢は、事業の経営者としてはあまりにも消極的であると思います。この姿勢は今もかわりはないのでしょうか。
次に、病院の建て替えでありますが、宝塚市立病院が目指す病院像においては、病院の建て替えが必要であるという結論が述べられただけで、具体的な計画は何も書かれていませんでした。施政方針では、新病院の建て替え場所の敷地調査を行ないつつ、現在の病院の更新工事も進めるというような、どっちつかずのことが書かれていますが、これは病院の建て替えをはじめとして、病院が抱えるさまざまな課題の解決を先送りしてきた大きなツケであると思います。病院の建て替えについて、どのような病院に建て替えるのか、その建て替えの時期等、一刻も早く検討し、決定するべきだと考えますが、現状ではどのような検討がなされているのでしょうか。ご説明を求めます。
5.魅力ある街作りについて
次に、魅力ある街作りについて質問をいたします。街作りについては、市政運営の基本方針の3つ目に、「協働」と「共創」で魅力のある街を築くということが示されています。また、本市の政策アドバイザーの意見として、「街作りには対話力と文化の自己決定能力が重要である」との意見が紹介されています。なんとなくそのいわんとするところはわかりますが、具体的な意味が明瞭でなく、本市がいかなる街作りを目指そうとしているのか、わかりにくいと感じます。特に、「文化の自己決定能力」とは何か、それが街作りのために、どのような意味で重要なのか、ご説明を求めます。
次に、本市が目指す街作りの方法ですが、基本方針の中で述べられているように、「全国的に高い知名度」や「華やかなイメージ」を生かすことが有効であることはわかります。そうすることで、若い世代の本市への転入を促進することができるだけでなく、本市の重要な観光産業の振興をはかり、街を活性化することが可能になります。しかし、私は、一民間企業がその事業として行なっている宝塚歌劇や、一個人の著作物である鉄腕アトムに過度に依存した街のイメージアップは、好ましくないと考えます。また昨年は、宝塚大橋の更新工事にともなって、橋の中ほどに設置されていたモニュメントを再び設置するか否かで、行政と一部の市民の間で議論が起りました。私は、特にモダンアートの作品に対する評価は人によって大きく異なるもので、そのようなものを公共施設に設置することは抑制するべきだと考えます。当局の認識はいかがでありましょうか。
魅力ある街作りのためには「華やかなイメージ」も大切ですが、宝塚は人口22万人の市民が暮らす住宅都市であることを忘れてはならないと思います。しかし、施政方針では、この住宅都市としての宝塚については何も語られていません。今、この住宅都市としての宝塚にとって、のどもとに突き刺さっている大きな問題があります。それはかつてのニュータウンであるところの山の手の住宅地が今やオールドタウンと化し、空き家が激増しつつあることです。空き家が増加すれば、街が寂れるだけでなく、交通機関や商業施設が衰退することで住みにくい街となり、さらに空き家が増加するという悪循環をもたらします。当局はこの問題についてどのように対処しようとしているのでしょうか。ご説明を求めます。
6.学校教育について
続いて、学校教育について質問をいたします。子どもが安心して穏やかに育つ街をつくることは、市政運営の基本方針の中でも最初に置かれていることから、その中でも最も重要な基本方針であると理解いたします。その中で、学校教育については、部活動、給食、いじめ対策などが個別の施策として取り上げられていますが、もう1つ、最も重要な施策として取り上げるべきことが抜け落ちているように思います。それは学校の授業や、児童・生徒の学習の問題です。本来学校とは児童・生徒が授業を受け、学んだことを身につけるところであると私は理解しておりますが、先生の授業のやりかたや、児童・生徒の学び方は、義務教育の学校では、明治時代から何も進歩していないと思います。旧来の画一的授業をやめ、児童・生徒の個性や学ぶ意欲、学習到達度に応じられるように、授業のやり方や学校のあり方も改革していくことが必要と考えますが、教育委員会の認識をご説明願います。
また、学年が進んでくれば、本人とご家庭の最大の関心事は何事にもまして上級学校への受験準備であろうと思います。最近ではそのために学習塾などへ通うことがすっかり一般的となり、ご家庭の負担は、心理的な負担だけでなく、経済的な負担も大変なものとなっています。これに対して、公教育の学校側では、公教育の外側にある学習塾などの存在について、今迄何らの関心も持とうとせず、むしろ敵視してきたのではないかと思います。しかし今や、学習塾に限らず、教育においては民間の教育機関の役割が非常に大きなものとなってきていることは、誰もが認識すべき段階に来ています。それでも教育委員会は、ご家庭が子どもを学校外の学習塾などへ通わせることについては、学校教育とは何ら関わりのない問題であるとして無視を続けるのでしょうか。教育委員会の認識をご説明願います。
学校教育について、私はもう1つ問題にしたいことがあります。それは教育委員会のあり方です。教育委員会が(もちろん事務局でない方の本来の教育委員会でありますが)形式上設置されているだけで、特別な仕事は何もしていない、ということは宝塚に限ったことではなく、昔からよく議論されてきた問題であると思います。実際、その議事録を見ても、発言しているのはほとんど事務方の出席者だけで、委員からの発言はほとんどありません。しかもその議事録が公開されるのは、委員会が開催されてから約2ケ月後というありさまです。私はイジメなどの問題については、委員からもっと積極果敢な発言があってしかるべきだと思いますが、まことに失礼ながら、今の教育委員会には期待できないように思います。教育委員会の委員の選任の仕方も含めて、教育委員会を活性化する方法を検討するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
7.市民の安全の確保について
最後に市民の安全の確保について質問いたします。市政運営の2つめの基本方針において、市民のいのちと暮らしを守ることが行政の重要なテーマとして語られていますが、それに関連する問題として特に、外国と戦争が起きたときに市民のいのちをいかに守るか、すなわち安全の確保の問題と、市民の暮らしを守るためのエネルギーの確保の問題について質問をさせていただきます。
まず、外国との戦争がおきたときの、市民の安全の確保について。この問題は、政府の外交努力の問題であって、市町村のレベルでそこまで考えても仕方がない、ということが、一般的な認識であろうと思います。施政方針においては都市経営の問題として「戦争と核兵器のない平和で安全な社会を築き後世に引き継ぐため・・平和事業を継続してきた」と述べられています。しかし、これだけで済ませてよいのか。ウクライナの戦争で明らかになったことは、外交努力など一切通用しない相手も存在するということです。最近ある市民から「宝塚市も市民のために核シェルターの建設を急ぐべきではないか」といわれたことがあります。私もさすがにそこまでやるのは現実的でないと思いますが、しかし、外国との戦争が現実におきてしまったときの市民の安全確保について、市は、ただ戦争がおこらないことを只バクゼンと期待するだけでよいのでしょうか。行政の認識をうかがいます。
次にエネルギーの確保について。エネルギーの確保が安全の問題として扱われることに奇妙な感じを覚える人もいるかも知れませんが、エネルギーは食料と並んで市民の生活に必要欠くべからざるものであり、その供給を確保することは、市民の安全に直結する重要な問題であると思います。この問題について、施政方針では、環境問題における脱炭素化の問題として、太陽光発電やバイオマス資源の活用が申し訳程度に述べられています。バイオマスガスなど取るに足りませんが、太陽光発電も、原子炉1つ分の100万kwのエネルギーを得るのに東京の山手線1周分の土地が必要といわれています。しかも夜間や天気の悪い日には何の役にも立ちません。行政には、目前に迫ったエネルギー危機に対する、もっと現実的な対応が求められているのではないでしょうか。水道と異なり、電気やガスなどのエネルギーの供給は、我が国では全面的に電力会社やガス会社などの民間企業に依存しており、行政とは直接かかわりのない問題であることは理解しています。しかし、もしその供給がストップしたときは多くの市民のイノチが危機にさらされます。今、原油価格の高騰などで、将来の電力をはじめとするエネルギーの確保が懸念されていますが、市は、市民のエネルギーの確保について、単に民間企業と市民との間の問題であるとして傍観しているだけでよいのでしょうか。行政の認識をうかがいます。(終わり)