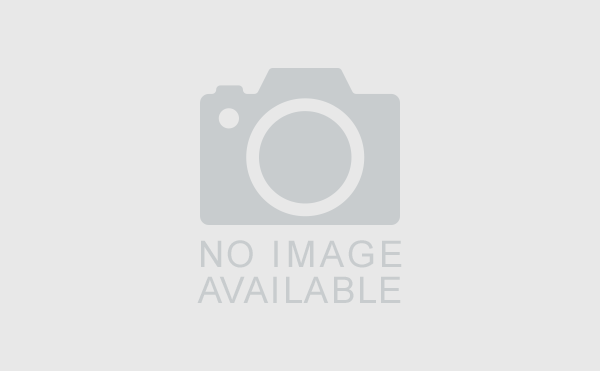12月宝塚市議会 一般質問
12月市議会の本会議場で行なった私の一般質問(一次)の全文です。
1.本市の財政悪化と今後の市政に及ぼす影響について
宝塚の財政は悪くなったとよくいわれますが、具体的にどう悪くなったのか。一部の議員がそのように言っているだけで、そんなに悪くなっていないのではないか。そう思っている人も多いのではないかと思います。実際、前の中川市長も退任後の新聞に対するインタビューで、「私は市の財政を悪化させたつもりはありません」と語っておられます。本市の財政当局もかつては、市民に対する広報誌において、実質公債比率などの指標が法律に定める基準の範囲内であることを以て、「本市の財政は概ね健全である」と強調していました。しかし一転して、昨年の広報宝塚11月号では「本市の財政状況は大変厳しいものである」と認め、今年の11月号でも再び「財政状況は厳しい」ことを認めています。そこでお尋ねしたいのですが、財政当局が、本市の財政健全化指標が法律に定める基準の範囲内であるにもかかわらず、「財政状況は厳しいと」認める理由は何でしょうか。
私も、宝塚市の財政状況が大変に厳しいものであると考えます。広報宝塚でも説明されているように、歳入面では、少子高齢化の進行により歳入の根幹である市税収入の伸びが見込めないこと、歳出面では、高齢化に伴い社会保障関連経費が増加すること、公共施設の老朽化に伴い、その維持管理費用も増加することなどがその理由です。要するに宝塚の財政をひとことで言えば、今はそれほど悪くなくとも、将来何ひとつよくなる要素がなく、悪くなる要素ばかりであるということにつきると思います。
宝塚の財政の最も象徴的な現象が、民生費の爆発的な増加と土木費の縮小であると思います。民生費は、昭和40年頃には、土木費や教育費とそれほど変わらない水準でした。その後、他市からの人口流入により、働き盛りの人口がどんどん増えていた昭和50年代から平成10年頃にかけては、土木費が300億円近くもあったのに対して民生費はその半分程度に過ぎませんでした。当時は潤沢な土木費で、JR及び阪急宝塚駅周辺の整備など、今では考えられないような大規模な公共事業を行なっていました。しかしその後、民生費と土木費は逆転し、民生費が爆発的に増加して今や400億円を突破しているのに対して、土木費は70億円程度の水準にとどまっています。
民生費は、社会保障関係費を中心とする費用であり、いわば行政が市民に支払うことを約束したおカネであって、少子高齢化にともない、これからもどんどん増加することは避けられません。一方土木費は、課題を先送りすることで支出を抑えることは可能です。またそうすることで、実質公債比率など、見かけの財政健全化指標の悪化を避けることも可能であり、「本市の財政は概ね健全である」などと取り繕うことができました。しかしこれからは、老朽化した道路、学校その他の公共施設の整備を置き去りにしてきたツケが、一気に噴出してくるであろうし、さらに、市街地再開発計画などの多くが実施されず、絵に描いたモチにとどまっているということもクローズアップされてくると思います。
財政当局は今後、民生費と土木費がどのように推移していくと予測しておられるのでしょうか。現状の推移で将来を予想する限り、民生費が引き続き増えて、土木費に回すオカネがなくなり、公共施設の維持管理も市街地の再開発もまともに実施できなくなると危惧いたしますが、財政当局はどのように考えておられるのでしょうか。
民生費の増加は本市だけの問題ではなく、日本全国の自治体に共通の現象であることは誰しもご承知の通りであると思います。しかし、本市の民生費の増加は日本全国の中でも際立っていると思います。地方財政白書によれば、令和元年において、全国の市町村の歳出総額に占める民生費の割合は37%であったのに対して、宝塚市は46%となっており、9%も高くなっています。この理由は何でしょうか。この状態をどのようにするべきでしょうか。財政当局の見解をもとめます。
2.宝塚市内の市街化区域における再開発の方針について
宝塚市における市街化区域とは、概ね西谷地区を除く平地部及び宅地化された高台の住宅地ですが、令和2年度の都市計画審議会では、中心市街地、売布周辺、小林周辺、山本周辺の4地区について、それぞれを計画的な再開発が必要な市街地とする、県による都市再開発方針の見直し案が承認されています。
この都市再開発方針の見直し案の中で、私が特に疑問に思っていることは、中筋JR南第2地区の再開発です。以下、中筋南第2地区と言いますが、ここはJR中山寺駅から南東方向に位置する伊丹市荒巻地区と接するエリアであり、その真ん中を南北方向に、交通量の多い県道中野中筋線が通っています。他に、旧国鉄の貨物線を転用したトロッコ道と呼ばれる道路があり、その道沿いにはおおきな病院や、保育園、スーパーマーケットなどがあり、浪速芸術短大へ通う多くの学生の通学路ともなっております。この中筋南第2地区が、都市再開発方針の見直し案によれば、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を進めるべき地区とされ、この地区で概ね5年以内に土地区画整理事業をすすめ、都市計画公園、都市計画道路を建設することとされています。しかしながら、そのような事業が進められる気配は今のところ全然ありません。これはなぜでしょうか。
そのほかに、市民の関心も高く、早急に再開発を進めるべきであるのに、再開発の始まる気配が全く見えない地区として、小林駅前地区があります。小林駅前地区は、都市再開発方針の見直し案によれば、計画的な再開発が必要な市街地の中には含まれているものの、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を進めるべきには指定されておらず、概ね5年以内に実施すべき事業が何も記載されていません。議会でもたびたび取り上げられてきたのに、中筋南第2地区などより低く格付けされているように見える、つまり当局に「再開発を急ぐべき」という認識があまりないように見えるのは、なぜしょうか。
そのほかにも、清荒神駅北地区など、都市再開発方針の見直し案によって、計画的な再開発が必要な市街地の中には含まれているものの、全く再開発に手がつけられていないように見える地域が複数あります。今迄の進捗状況及び、市の財政事情を考えるとこれから再開発が実現することはほとんど期待できないように思えるのですが、当局はどのように考えておられるのでしょうか。説明を求めます。
3.新ごみ処理施設の建設について
現在稼働中のごみ処理施設は、通常25年といわれる耐用年数を大幅に経過しながらも、その更新をどうするかがなかなか決まらず、心ある多くの市民にご心配をかけてきたところですが、今年の9月になってようやく川崎重工をはじめとする企業グループに発注することが決まり、一安心というところだと思います。個人的な感情になりますが、サラリーマン生活37年のうち、20年間を神戸のサラリーマンとして過ごした私にとっても、神戸を代表する企業に発注先が決まったことは、なんとなくよかったという気持ちでおります。
今後残された最大の課題は、整備工事で総額428億円、24年間の運営で総額195億円という、本市にとっては巨額の費用をまかなうことですが、これまで何度も、財政当局をはじめ関係責任者が「大丈夫だ」と胸を張って答弁されてきましたので、その点は信用するしかないと思います。今ここでは、その点を除いて、私なりに感じた素朴な疑問について質問をさせていただきます。
まず、入札企業が1社となってしまったことについて。ごみ処理プラントは、ユーザーが市町村のような自治体に限られ、しかも新規の需要はほとんどなく、2~30年に1度の更新需要しかないという、非常に特殊なマーケットであると理解しております。このマーケットにサプライヤーとして参加している企業は少なく、まして大規模なごみ処理施設を受注し、とりまとめができるような企業は限られている、従って入札に応じる企業がそんなに多くはない、ということはあらかじめ予想されたことであったと思います。しかし、入札企業が1社だけというのは、何か問題があるように感じるのが普通だと思います。
公共工事の入札において、1社だけの入札となってしまった場合には、談合などの不正が行われた疑いを排除できないため、あるいは落札価格に企業間の競争が反映されないため、一般競争入札における1社入札を無効とする自治体があります。本市ではそのようなルールがないために、本ごみ処理施設の入札は1社入札でも有効な入札として取り扱かったものと理解いたしますが、この考え方の根拠をお聞かせください。
次に、焼却炉の形式がストーカー炉であることについて。ごみ焼却炉の形式については、大きく2つに分けて、ストーカー炉とガス化溶融炉があるといわれております。ストーカー炉とは、ストーカーと言われるグリルの上にゴミを乗せ、下から空気を送ってゴミを燃やしてしまう方式であり、言わば単純にゴミを燃やすことに他なりません。一方ガス化溶融炉は、ゴミを高温でガス化溶融することにより、スラグ・メタルといった有効利用可能な資源に変えるシステムです。
ガス化溶融炉の方が、建設コストや運転管理のためのコストが少し高いというデメリットはありますが、ごみを燃やしたあとの灰の発生がなく、ごみを有効利用可能な資源に変える点で、マテリアルリサイクル、地球環境保全の点において優れていると言われます。近年、ごみ処理プラントメーカーにおいて熱心に研究が進められており、実は私が在籍していた神戸の民間企業でも、工場の中にパイロットプラントを建設して熱心に研究していました。本市がガス化溶融炉の導入をしなかったのはなぜでしょうか。
次に、財源の問題について。さきほど財源の問題については、財政当局が何度も大丈夫と胸を張って答弁してこられたので、それを信じるしかないと申し上げたところですが、ごみ処理施設は無事に建設できたとしても、それ以外のところにシワ寄せがいくのではないかという心配は残ります。たしかに財政当局が作成した「新ごみ処理施設整備事業資金計画表」を見る限り、合計463億円の整備費用は問題なく調達でき、市の財政がそれによって破綻することはなさそうに思います。しかしながら、問題はその財源の出所にあります。463億円は、国からの交付金及び地方債と一般財源でまかなうことになっていますが、そのために都市計画税としての税収の多くが、25年もの長期間にわたって、多いときで10億円以上利用されることになっています。都市計画税としての税収は毎年30億円程度しかありません。それだけの長期間にわたり多くの都市計画税をごみ処理施設の整備事業につぎ込むことは、本市の今後のインフラ整備の障害とはならないのでしょうか。これから本市が整備を進めるべきインフラには、道路、学校、水道、病院など数え切れないほどあると思いますが、その中でも特に市立病院の建て替えは、大きな負担となることが予想されます。ごみ処理施設につぎ込む都市計画税を少しでも減らす方法をも検討するべきであり、そのための方法はあるのに、なぜ検討もしないのかと私はフシギに思っております。(終わり)