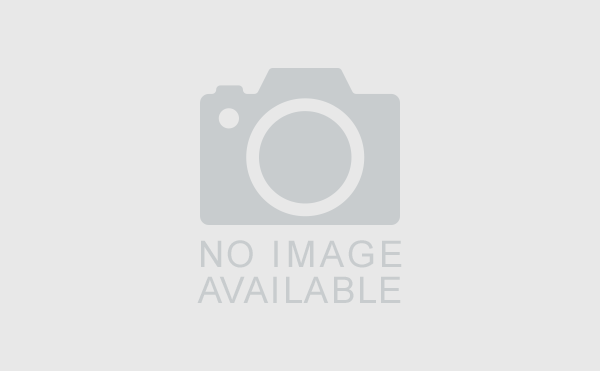宝塚市議会一般質問 オープンはどこに
6月15日の市議会で一般質問を行ないました。以下は1次質問の原稿です。
1.今年の施政方針:3つのオープンはどこに
今年度の施政方針をお聞きしておりまして、私が強く感じましたことは、昨年の施政方針と比べて、革新陣営的なトーンといいますか、色合いがほとんどなくて、逆に保守陣営的といいますか、保守的な官僚が好んで使いそうな表現がいくつも目についた点であります。特に「市民自らが我が身を守る自助、地域の力でお互いの命を守る共助の備えも大切です」と市長が言い切られたあたりは、ビックリするぐらい印象に残りました。かつて総理大臣がその就任の挨拶で「国民の自助努力も大切」と述べたとき、野党陣営から一斉に、「行政の責任を放棄するもの」「弱者に寄り添うつもりがないもの」として、激しい批判を招きました。今日、国民や市民に向かって自助努力を求めるなどということは、政権担当者もしくは保守系の政治家がすることであって、革新陣営はこれに反発するのが一般的です。したがって山崎市長が施政方針の中で「市民自らが我が身を守る自助も大切」と言われたことは、もしかすると山崎市長は革新陣営を離れ、中川施政からの脱却も目指されているのではないか、と考えざるを得ませんでした。山崎市長はかつてこの議場で、「私は中川市長の後継者ではない」と述べられたこともあります。果たして山崎市長は「中川市政からの脱却を目指されている」と、理解してもよろしいのでしょうか。
私自身は、「我が身を守る自助、地域の力でお互いの命を守る共助も大切」と市長が言われたことにビックリはいたしましたが、言われた内容そのものはあたり前のことだと思っています。私たちは子どものときから「自分のことは自分でせよ」といつも教えられてきました。「我が身を守る自助」が大切なことは当然です。「地域の力でお互いの命を守る共助」とは、地域住民の助け合いのことであろうと思いますが、これも当然です。ただ、「地域の力」とは一体何なのか。「誰に何をせよ」と言っているのかが具体的ではありません。宝塚には、地域の住民が組織する団体として「自治会」と「街作り協議会」がありますが、いずれの役割も明確ではなく、そこに悩みを抱えている自治会の役員さんもおられます。どちらに何をせよと言っているのか、明確にしておく必要があると思います。
今年の施政方針は、そのトーンが大きく変わった一方で、昨年の施政方針で基本方針として示され、市長選挙でも繰り返し使用された、オープンというコトバの入ったスローガンが、一度も登場しませんでした。「あなたにオープン」「教育をオープン」「暮らしと経済をオープン」という3つのオープンは一体どこに行ってしまったのでしょうか。この3つのオープンは単なるスローガンではなく、市長の選挙公約でもあって、市長には他に公約らしい公約もないので、1年たったからといって用済みにできるものではないはずです。昨年は、市長はまだ就任されたばかりであって、市長就任後の補正予算では、これらの公約実現に向けた予算の肉づけがほとんどなかったのは仕方がないと思いますが、今年はそれらの公約の実現に向けた努力があってしかるべきだと思います。しかし、今年度の施政方針ではオープンというコトバが一度も登場してこなかったのみならず、新年度予算を見ても、3つのオープンの実現を目指した予算措置が一体どこで為されているのか、ほとんどわかりません。そこでお尋ねいたします。3つのオープンの中でも特に「あなたにオープン」について。このスローガンで市長が意図したことは何であったのか。このスローガンで意図したことは、今後どのように実現していくつもりなのか、ご説明願います。
2.行政・財政・職員人事もオープンに
次に、行政・財政・職員人事に関するテーマにうつります。今、政治の世界では、行政のさまざまなプロセスを、市民の誰にもよく見えるようにオープンにすることが、大きな潮流となっているように想います。山崎市長は「あなたにオープン」を旗じるしとして市長に当選されましたが、市長がオープンにするべきものとして想定しているのは、既に行政が保有している公開しやすい情報か、もしくは教育などごく一部の行政のプロセスに過ぎないように思います。私は、行政、財政、そして職員の人事に至るまで、あらゆる行政のプロセスをオープンにしていくことが、行政に民意を反映し、正しく行政が行われるために必要であると考えます。
行政のプロセスの中でも特にオープンにする必要性が高いのは、予算案作成のプロセスであろうと思います。予算案は、行政のあらゆる部分に関わる、とてつもなく複雑で大きな議案ですが、議会にはいきなり、いわゆる市長査定を終えて確定した予算案が示され、議会は、新年度の予算執行が迫っている中で、あわただしく審議し、採決しなければなりません。予算特別委員会では、熱のこもった質疑応答が展開されますが、予算案の修正が必要になるような意見はほとんどなく、「この段階でそんなことを言っても仕方がない」ということが議員共通の認識になっているように思います。国における予算案作成のプロセスを見るならば、政府予算案が内閣で決定されるまでの途中の段階で、概算要求や財務省原案が公表され、これらに対して各政党はヒアリングや勉強会を重ね、非公式な形で、関係省庁に提言、意見の陳述などの働きかけを行なっていきます。
市の予算案作成においても国の予算案作成と同じように、各部局の概算要求や市長査定前の財務部がとりまとめた原案を公表し、会派もしくは議員個人に、たとえ非公式な形ではあっても、意見を述べる機会が与えられることが必要であると考えます。また、市長は予算案の作成に強い権限をもって関わっているはずなので、予算案のどの部分が、市長のいかなる政治的判断により予算化されたものであるか、あるいは修正を受けたものであるかが明示されることが必要であると考えますが、いかがでしょうか。
ごく日常的な行政のプロセスについては、法律や条例にもとづいて正常に行なわれているかぎり、いちいちオープンにして手間をかける必要はないと思います。しかし時として、行政の中にも、市長の特別な政治的判断に基づいて実行される、前例のない行政があります。最近では、中川前市長時代に実行された、就職氷河期世代の職員採用がそれに該当すると思います。特に予算措置も必要がなかったことから、議会も知らないところで、市長と行政の担当者の判断だけで実行されたものと思いますが、私などはマスコミで発表された後で知って、いささかビックリしてしまいました。そのような、市長の政治的判断に基づく重要な行政の実行は、たとえ法律や条令で定められた手続きとして必要がなくとも、議会に事前説明し、議員にも意見を述べる機会が与えられるべきであると考えますがいかがでしょうか。
「行政のあらゆるプロセスをオープン」と言っても、職員の人事までオープンにすることは、ゆきすぎであると感じられるかもしれません。しかし、人事は、情実によることなく、明確なルールと客観的な評価に基づいて行なわれるべきであり、このような透明性と客観性を確保するという意味で、人事をオープンにすることは必要であると思います。この点、前中川市長が職員人事について、「最終的には私が判断しております」と答弁されたことがありますが、私は職員の人事に市長の政治的判断が介入することは、人事の透明性と客観性を損なうものであり、好ましくないと考えます。あのモリカケ問題が審議された国会で、本来優秀なはずの政府の官僚が、誰が見ても明らかな事実を「記憶にございません」などとトボケ、見え透いたウソをつくといった光景が繰り返されたことは、日本の憲政史上最も恥ずべき、忌まわしいできごとであったと思います。これは行政に対する政治のガバナンスを理由として、内閣人事局、つまり時の総理や官房長官が官僚の人事に介入するようになったからだと言われています。市長の職員に対する人事権については、地方自治法第154条で「地方公共団体の長は職員を指揮監督する」と定められていることが根拠とされます。しかし、このように定められているとしても、市長は一般職員に対する人事権の行使を差し控えるべきであると考えますが、いかがでしょうか。
3.市長の議会での答弁もオープンに
行政・財政のプロセス、そして職員の人事もオープンにするべきである、と述べてきましたが、これらのこと以上に、オープンにしていただきたいことがあります。それは市長と職員の議会に対する対応です。特に市長は行政のトップであり、さまざまなところで有形無形の権限を行使しているはずですが、その肝心の市長が何を考え、それがどのように市政に反映されたのか、せめて議会の答弁で明らかにしていただく必要があると思います。
私は、去る3月の予算特別委員会の最終日で、5つの質問をさせていただきました。私は、できるだけ市長自身の考えをお聞きしたいと思い、前日のうちに質問事項をペーパーにまとめて秘書課に提出しておきました。いずれの質問も、市長ご自身の基本的な考え方をお尋ねするものですが、内心では「市長がひとりで全部答えるのはシンドイかもしれんなあ」と思っていました。ところがそのような心配は全くの杞憂でありまして、いずれの質問も市長はご自身で答弁することなく、3人の部長が代わる代わる答弁されました。最後の1問ぐらい、市長の考えをお聞きしたいと思って「市長はどう思うか」と強く答弁を求めたところ、今度は副市長が答弁されました。市長ご自身の指示によるものかどうかはわかりませんが、私が提出した質問状の写しが関係部長に配られ、市長の代わりに答弁をするように指示されたのであろうと想像します。
そもそも宝塚の市議会には、今となってはハッキリしないようですが、少なくとも一部の議員の間では、「市長に答弁を求めるべきではない」という申し合わせらしきものがあったとお聞きします。それが最近になってようやく、ごく控え目ながらも議員が市長の答弁を求めるようになり、その点ではやっと本市議会も普通の議会らしくなってきたと、私は思っています。ところが、議員が市長に答弁を求めたとき、すかさず部長の誰かが手を挙げ、その質問に答えてしまわれることが多いのです。これは一体どういうわけでしょうか。幹部職員の間で、市長はまだ答弁に慣れていないから、「職員みんなで市長を支えよう」という申し合わせがあるのかも知れません。あるいは、自分の守備範囲に属する質問が来たら、それが市長の答弁を求めるものであっても、仕事に対する責任感から、「自分が答えるのが当然」と感じてて答弁されるのかもしれません。しかし、市長の答弁を求めた議員としては、「市長の考えを明らかにする必要がある」と思って、市長に答弁を求めているのであり、議員の意図は尊重されるべきだと思います。
たとえ市長の答弁を求める質問であっても、それは行政に向けられた質問であるから、「市長が答弁しても職員が答弁しても同じ」と考えてもよいケースは多いと思います。行政の大部分は、法律や条例に基づいて、あるいは担当した職員の技術的・専門的な判断に基づいて行なわれるものですから、そのような行政に関する質問なら、所管部の担当者が答弁するのがふさわしいと思います。しかし、行政の中には市長の政治的判断によって実行されるものがあります。山崎市長はかつて、「私は政治家ではなく市民の代表」と胸を張って述べられたことがありますが、このコトバは、「市長は市役所のトップとして、市民全体のために働くもの」という意味で理解することはできます。しかし市長は、選挙で選ばれた以上はやはりは政治家であって、その判断には政治家としての判断がつきまとう-わかりやすく言えば「自分の支持者達の顔色を伺いながら政治的な判断をする」ということは多々あるはずです。
まさにそのような市長の政治的な判断こそ議会で審議されるべき事項であり、それがいかなるものであるかを明らかにし、正しいか正しくないかを議論することが、議員の最も重要な仕事であると、私は思っています。そのような市長の判断に対する質問は、市長自身でなければ答弁できないはずであり、市民にとっては次の市長選挙の重要な判断材料にもなるものです。地方自治法は第121条で、市長の議会に出席する義務を定めているだけであり、どのように答弁するべきかまでは定められていません。しかし、市長は、議会に出席される以上は、十分に存在感を発揮され、「あなたにオープン」というご自分のスローガンにふさわしい答弁をするべきであると考えますが、いかがでしょうか。(終わり)