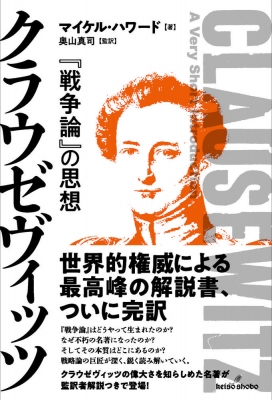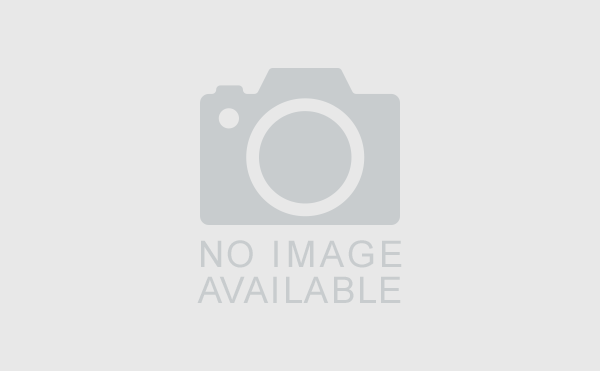戦争も外交の手段?
「戦争も外交の一つの手段である」(クラウゼヴィッツ:戦争論)とする考え方がある。大学の法学部で学んだ人なら、聴いたことがあると思う。今、こういう極端な考え方をする政治家はあまりいないと思うが、これを当然と考え、実践する政治家もいる(プーチンなど)。プーチンはKGB(旧ソ連の特高警察)出身で、民主主義のカケラも理解しているはずがない、と私は思っていた。こんな人物を相手に、我が国のアベ首相などは、一生懸命ゴキゲンを取って領土返還交渉などをしていたのだから、なさけないにもほどがある。プーチンにすれば、どさくさ紛れとはいえ、祖国が戦争でぶん捕った領地をおめおめと日本に返せるはずがないではないか。
軽い言い方で済ませるのは忍びないが、ウクライナの惨状は想像をはるかに超える。手当たり次第に民家を破壊し、住民を虐殺するなど、ナチスドイツもやらなかったことではないか。目的(理想の共産主義社会を実現する)のためには全てが正当化される、とするレーニンやスターリンの思想が未だに根底にあるようだ。第二次世界大戦におけるソ連の犠牲者は2600万人といわれる。しかし、スターリンによって「共産主義に反逆する罪」に問われ、銃殺されたり強制収容所でなくなった人はそれ以上といわれる。
左翼系の人々はとりあえず「戦争反対」と言っているようであるが、この戦争は「どっちもどっち」の戦争ではない。ロシアに向かって「侵略戦争をやめよ」という意味なら、それは正しい。しかし、ウクライナに向かって「武器を置いて抵抗をやめよ」という意味も含むとすれば、それは完全に間違っている。今、ロシアとウクライナとの間で中途半端に和平が実現したとしても、恒久な平和にはなり得ない。私は、ウクライナ(+西側諸国)が徹底的に戦い、この戦争に勝利してプーチン体制を抹消する以外には、真の平和はあり得ないと思う。
この戦争を見て、国家や憲法について改めて考えた人も多いのではないか。私は、今の現行憲法でも、自衛隊というものが存在し、自衛権を行使して国を守ることができるのであれば、無理に憲法を改正する必要はないと思っていた。しかし、今のロシアのような国が今後も存続するなら、現行憲法ではとてもやっていけないと思う。いざというとき、何をやるにも憲法上の議論が必要になり、間に合わなくなってしまう。少なくとも自衛隊は軍隊であること、国に交戦権があることをはっきり認めるべきである。そして、国家存亡の危機において、国民に国を守る義務があることも明記するべきではないか。全国民が軍隊に入って戦う必要はないにしても、国民の一人一人が国家存続のために何らかの責任を果すことは当然であると思う。