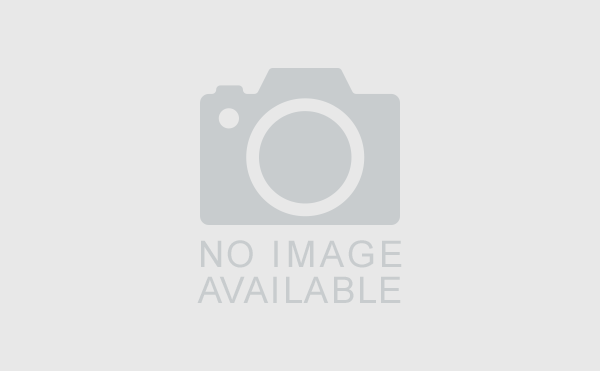宝塚市長の市政に取り組む姿勢
12月8日、宝塚市議会で、山崎市長の市政に取り組む姿勢について、批判的に質問をしました。原稿用紙12枚程度の分量になりますが、宝塚市政に関心のある方は読んでみてください。

無所属の会、田中大志朗でございます。
本日は、山崎市長の市政に対する取り組み方について質問をさせていただこうと思います。批判のための批判は避けた上で、山崎市政について、私の思っていること、感じたことも、遠慮せず率直に述べさせていただこうと思っております。
山崎市長が就任されてから半年あまりが過ぎましたが、不思議なことに、「あなたにオープン」といって就任された市長のお仕事ぶりがよく見えません。市長が何を考えてどのように行動されているのか、つまり山崎市政とはどのようなものかが、よくわからないのです。山崎市長は何がやりたくて市長になったのか、と疑問に思っている市民も少なくないと思います。
山崎市長の前は、山崎市長と同じく革新系の中川市長が3期12年間、市長を務められました。しかしその間、福祉や学校給食などに力を注がれたものの、財政は悪化し、深刻ないじめや教員の不祥事が多発するなど、様々な問題が未解決のまま残されました。これは中川市長が、市政の問題点や、市長がやるべきことは何か、ということを十分認識されていなかったことにも原因があると私は思っています。
まだ始まったばかりですが、山崎市政がそうならないように、しっかり注目していかなければなりません。そして、本日の質問を通じて、山崎市政とは一体どのようなものか、少しでもオープンにしたいと思っております。
私は、市長には2つの側面があると思っています。それは市役所という行政組織のトップとしての側面と、公約を掲げて選挙で選ばれた政治家としての側面であります。まず、行政組織のトップとしての市長について、質問をさせていただきます。
1.行政組織のトップとしての市長について
(1)組織のトップには何が必要か。まずリーダーシップが必要なはずです。市役所のような組織におけるリーダーシップとは何か。これは、民間企業でも同じだと思いますが、部下に的確に指示を与えたり、報告を受けて問題点をただしたり、場合によっては叱責を与えるというようなことを、部下との信頼関係を維持しながらやっていくことだと思います。そのようなことは一朝一夕にできることではなく、組織の一員として、特に中間管理職として苦労した経験が必要だと思うのですが、山崎市長には、そのようなご苦労をした経験があまりないように見受けられます。果たしてそのような市長が、組織のトップとして、リーダーシップを発揮していただけるものかどうか、多くの人が心許ないと感じているのではないでしょうか。
そこで質問ですが、市長の市役所のトップとしてのお仕事ぶりはどのようなものであるか、特にどのようにリーダーシップを発揮しておられるのか、お聞かせください。
(2)組織のトップには、リーダーシップ以上に、仕事に対する知識と経験が必要だと思います。民間企業の社長ならば、20年、30年と経験を積み重ねてきた社員の中から選ばれるのが通例ですが、選挙で選ばれる市長は、行政に対する知識も経験も乏しい人がいきなり選ばれるケースが増えてきました。そんな自治体では、市長の仕事は、議会での答弁を含め、ほとんどすべての仕事が、副市長以下の行政職員にまかされがちのようですが、そんな市長なら誰がやっても同じです。山崎市長は弁護士としての資格は持っておられますが、市長として必要な知識と経験は別問題であり、私は一日も早く、市の行政の全体像や深刻な現状を理解していただきたい、と思っております。
つい先日行なわれた決算特別委員会はそのための絶好の機会であり、委員はみな、電話帳のような分厚い決算成果報告書を読み込んだ上で、連日真剣に質問を行っていました。市長は第一日目と最終日以外は欠席されましたが、そこで真剣に議論された内容は把握しておくべきだと思います。そこで質問ですが、市長は、宝塚市の行政の全体像や深刻な現状は、すでに十分理解しておられるのでしょうか。決算特別委員会で審議された内容は、十分把握しておられるのでしょうか。
(3)組織のトップには、リーダーシップや仕事に対する知識と経験以上に、ヤル気が大切だと思います。市長にヤル気がなければ行政は何もかわらないと言われます。そんな市長のヤル気は予算案に示されるはずです。予算は行政の事業計画そのものであり、もし、予算案の中に、市長の発案で予算化した部分が何もないとすれば、それは市長にヤル気がないということになります。
市長が就任されて間もない6月に開催された予算特別委員会は、新たに就任された市長が予算に肉付けを行なうために開催されたものですが、このときの予算案には、市長の発案で予算化されたものはなかったと思います。「市長の発案で予算化されたものは何か」という私の質問に対して市長は、「時間的都合で予算化できなかったので、今後検討する」という趣旨の答弁をされたものと記憶しています。しかし、その後何度も作成された補正予算案の中にも、市長の発案により予算化されたと思われる部分は、なかったように思います。
そこで質問ですが、市長が就任されてから今までに何度も作成された補正予算案の中に、市長の発案で予算化されたものはあったのでしょうか。もしないとすればそれはなぜでしょうか。
2.政治家としての市長について(特にスローガンについて)
次に、政治家としての市長について、質問をさせていただきます。市長とは、選挙で掲げた公約を評価されて選ばれた以上、その公約の実現に向けて努力をしているかどうかが、問われなければなりません。山崎市長の場合は、具体的な公約があまりなく、その替わりに印象的な3つのスローガンを掲げられましたので、それぞれのスローガンに合致した施策が、果たして行われつつあるか否かについて、お尋ねしたいと思います。
(1)あなたにオープン:
まず市長は、「あなたにオープン」というスローガンを掲げられましたが、この意味は、市長の施政方針によれば「市民と行政の双方向の正確な情報共有を行うこと」であり、そのためには「市が今行なっていることを市民に正しくお伝えする」だけでなく「市民の声を聞くことも必要」であると述べられています。
ア)「市民の声を聞くために必要なことは何か」という私の質問に対して、市長は、「できる限り市民の皆様の要望、苦情などの意見を現場まかせにせず、私自身が目を通すことが必要」さらに「窓口に備え置きのはがきによって提出されたご意見などは、全て私自身が目を通した上で回答を差し上げ、必要によって担当部署に指示を行なっている」と答弁されています。この答弁で述べられたことが「あなたにオープン」というスローガンの具体的な内容になると思いますが、市長はどの程度実行されているのでしょうか。
イ)「市民と行政の情報共有の場、あるいは仕組みとして、市民の質問があれば答えるというようなあたり前のことだけでなく、何か新しい方法を考えていますか」との私の質問に対して、市民交流部長は、「現時点では、まだ具体的な新たな施策の検討には着手していない」と答弁されています。そこで質問ですが、市民と行政の情報共有の場、あるいは仕組みとして、その後新しい施策は検討されたのでしょうか。
(2)教育をオープン:
ア)市長は2つ目のスローガンとして、「教育をオープン」というスローガンを掲げられています。この内容として市長は、施政方針の中で「子供の声をもっと受け止めることができるよう、教育現場を整えていく」と述べていますが、私は、それだけでは抽象的で、内容も乏しすぎると思います。私は、教育をオープンにすることの内容として、
①校庭をオープンにする・・放課後も学校の校庭で、児童が夕方まで自由に遊ぶことを認めること
②教室をオープンにする・・学習塾や各種習い事の指導者に、学校のアキ教室の利用を広く認めること
③授業参観をオープンにする・・日時を限定せずに保護者・関係者に授業参観を広く認めること
なども十分検討する価値があると思います。内容的に教育委員会の所管になると思いますが、市長の施政方針に大いに関係する内容なので、市長自身の考えもお聞きかせいただきたいと思います。
イ)市長が教育に対して、ご自身の強い思いがあることは理解できますが、市長と教育委員会との関係において、制度上、それを直接市長自身の手で実現することはできないと考えられます。なぜなら、教育については政治的中立性や継続性・安定性の確保が必要なため、教育に関する事務は、市町村などの自治体では、市長から独立した教育委員会が責任を負っています。教育委員会が所管する教育事務については,市長の指揮命令権は及ばず、市長は教育委員の任命や予算編成などを通じて間接的に責任を負うにすぎない、とされております。簡単に言えば、市長は教育に関しては、カネは出してもクチは出せない、ということになっております。そのような教育委員会と市長との関係の中で、市長は、ご自分の教育に対する思いを、どのようにすれば実現できると考えておられるのでしょうか。
(3)暮らしと経済をオープンについて
最後に、市長の「暮らしと経済をオープン」という3つめのスローガンは、これだけを見ていても意味がよくわかりません。暮らしと経済の何をどのようにオープンにするのか、市長がオープンにしたいものは何かを、明らかにしていただきたいと思います。(終わり)