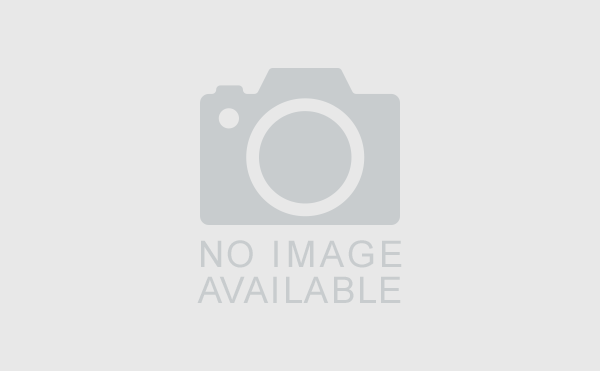宝塚市議会一般質問 小中学校教育について
9月29日、私が宝塚市議会本会議場で行った一般質問です。分量は400字詰原稿用紙14枚程度です。

市内の小中学校の先生方は、このコロナ禍で毎日大変なご苦労をされていることと思います。まずそのことに、市民の一人として感謝申しあげたいと思います。本日私は、このコロナ禍ではありますが、あえて、昔も今も変わらない、教育上の大きな問題について質問をさせていただこうと思います。私も人並みに、少年時代は小学校、中学校に通学いたしました。また一人の親として、自分の娘を小学校・中学校に通わせました。当然、教育を受けた本人として、またその親として、教育に対する思いは多々あります。本日はその思いを率直にぶつけるつもりで、質問をさせていただきます。
宝塚ではこの数年の間に、教師の暴力やいじめなどの事件がタテ続けに発生し、教育に対する信頼が大きくゆらぐ事態となりました。私の近所の中学校で起きた柔道部の先生による事件では、「まったく今の先生はどうなってしまったのか」と思わざるを得ませんでした。このような深刻な事態に対応するべく、山崎市長は「教育をオープン」というスローガンのもとに、教育改革を進めることを施政方針として示されました。「これで宝塚の教育はきっと改革される」と、多くの皆さんが一安心されたことと思います。
しかし、私には「ちょっと待てよ」という大きな疑問が残りました。「これでいじめや教師の暴力はなくなるかもしれない、しかしそれはあたり前のことではないのか。肝心の勉強の方は大丈夫なのか」という疑問です。先頃、新市長の誕生に続いて教育長も交代されました。その就任挨拶の中で、新教育長が、いじめや教師の暴力などの問題に取り組む覚悟を示されたことは、当然のことと思います。しかし、その挨拶の中に、「勉強」もしくは「学習」というコトバがひとこともなかったことは、私には実にフシギなことに感じられました。学校から教師の暴力やいじめをなくすのは何のためか。それはもちろん、生徒のイノチや人権を守るためです。しかし、それだけで足りるのか。学校は何をするところかを考えれば、「生徒の学習する権利を守る」ということも忘れるべきではないと思います。
ここで、専門家ではない私が言うのも僭越ですが、日本の教育の歴史をひとことで言うならば、それは「教育の平等を目指す歴史」であったと思います。明治5年に小学校が義務教育と定められたとき、授業料はタダではありませんでした。義務教育でありながら、小学校に行くことができない子供もたくさんいたといわれます。それが戦後になって、授業料や教科書も無償となり、昭和30年代も終わる頃には、義務教育だけでなく高等学校への進学も一般的になったといわれます。
かくして教育の平等が実現してゆく中で、新しい形の不平等が問題になりました。いわゆる学校格差です。同じ公立高校の間で、いわゆる名門校や新設校などと格差があるのはケシカランという声に押され、東京や兵庫県などの都市部で、学校群制度、総合選抜制、小学区制などの格差をなくす措置が、強引に進められました。私なども昭和40年代の半ば頃、大阪府下の公立中学3年生でありましたが、夏休みが終わる頃、突如として高校の通学区域が分割され、市内にある公立の伝統校の受験ができなくなってしまいました。まさにオリンピックが中止になるのと同じくらいのショックであったと思います。
その結果がどうなったかは、ご存知の通りであります。公立の名門高校はみんな没落して個性のない平凡な学校になってしまい、そのかわりに受験指導に力を入れていた私立の進学校が台頭しました。私立の進学校では中高一貫制を採用しているため、子供の勉強に熱心な家庭では、子供を学習塾に通わせ、中学受験をさせることが一般的になりました。まさに受験戦争が低年齢化したわけであります。そして中高一貫の私立の学校が、デキル子供をかき集めて超進学校へと変貌しただけでなく、私立中学と公立中学との間にとんでもない格差ができてしまいました。皮肉なことに、高校の格差をなくそうとした結果が、新たに中学校の格差を生んでしまったことになります。
宝塚を含む阪神地区で、小学校から高校にかけての教育が、このようなありさまになってから既に50年以上が経過しております。「デキル子が中学から私立に行くのは宝塚の風土だ」といった元小学校の先生もいます。我が子を少しでもよい学校に入れたいという親の気持ちは当然です。しかし私は、今の私立の中学と公立中学との格差は、単に学校間格差にとどまらず、生徒本人によっては克服しがたい大きな教育格差をもたらしていると思います。私立の中学校に進んだ生徒が、裕福な親のおかげで恵まれた教育を受けることは、それはそれで大いに結構なことであります。その反面、公立中学に進んだ生徒が、何らの選択の余地もなく、一方的に画一的な教育しか受けることができないとすれば、それは大きな不公平であります。このような不公平は絶対に正さなければならない、との強い思いから以下の質問をさせていただきます。
1.市の教育委員会では、市内の小中学生が、いわゆる学習塾に通っている割合、それと市内の公立小学校を卒業した生徒が、私立の中学校に進学する割合を把握しておられるでしょうか。これらは、今日の教育に関わる大きな社会現象であり、教育行政のあり方を左右する問題でもあると思います。また、授業をする学校の先生方にとっても、どの生徒が学習塾に通っているか否か、またそこでどの程度の勉強をしているかは、把握しておくことが望ましい生徒の学習環境であり、生活環境でもあると思いますが、いかがでしょうか。
2.次に、市内公立小中学校の授業についておたずねします。学校の授業と言えば、1人の先生が、1クラス40人前後の生徒に対して、一方的に知識を授ける形の、いわゆる一斉講義型の授業が中心になってきたと思います。このような形の授業は、明治の昔から今日まで、ずっと変わらずに続いてきたものと思いますが、その一方で、熱心な先生によって、さまざまな授業に対する工夫もなされてきました。最近になって、文部省がアクテイブラーニングなるものを提唱しましたが、これに対する先生方の意見や対応は様々であるとお聞きしております。いずれにいたしましても、学校の授業は、個々の生徒のニーズに対応したものにしていく必要があると思いますが、市の教育委員会は、どのように考えておられるのでしょうか。
3.続いて、ただ今の質問に関連致しますが、中学校で、いわゆる習熟度別授業ができるか否か、おたずねいたします。門外漢の私が言うのは僭越ですが、中学校で学ぶ教科の中でも、特に英語と数学は、意欲を持って取り組む生徒とそうでない生徒の違いが大きく、全員が同じ授業では、デキル生徒には退屈な授業となり、そうでない生徒にはワケがわからないまま終わってしまいます。生徒を、優等生とそうでない生徒に完全に分けてクラス編成をすることは、さすがに差別感情や劣等感を生んでしまって、弊害が大きすぎると思います。しかし、科目を限定して習熟度別の授業をするだけなら、そのような弊害もあまりないと思います。習熟度も生徒の個性であって、習熟度別授業は生徒の個性に対応した合理的な授業であると考えれば、教育の平等の原則にも反するものではないと考えますが、いかがでしょうか。
4.続いて授業に関する質問ですが、通常の授業ではあきたらず、もっと勉強したい、という生徒に対して、その意欲に応えてやることができるか否か、おたずねいたします。現在の宝塚市内の小中学校では、残念ながらそのような生徒への配慮が全くなく、まるで「もっと勉強したかったら、かってに塾に行ってください」と言わんばかりの対応になっています。これでは、経済的に裕福ではない家庭の子供は、学ぶ権利を奪われているのとおなじであり、学校は教育責任を十分に果たしていることにはならないと思います。発展的な内容を学習する場として、特別授業などができればそれに越したことはありませんが、せめてクラブ活動のような位置づけで、生徒が学習する場を設けてやることは可能ではないかと思います。東京のある公立中学では、大学生などのボランティアに先生をお願いして、学校内にいわば無料で参加できる学習塾を開設しているということであり、これも1つの方法だと思いますが、いかがでしょうか。
5.次に、授業をする先生について質問いたします。最近では先生による不祥事が相次いで起きることから、多くの市民が強く心配するところですが、今や先生にも様々な先生がいると言われます。大ベテランの先生もいれば、社会人としての経験も足りない未熟な先生もいるし、授業に全力投球の先生もいれば、そうでない先生もいる。中には生徒とのコミュニケーションも満足にできない、指導力不足の先生もいるとお聞きします。しかも、生徒は先生を選ぶことができないため、どの先生に当るかで、勉強する機会が不当に奪われてしまう、ということにもなりかねません。本来、指導力不足の先生など学校に存在してはならないと思いますが、実態はいかがでありましょうか。。
6,次の質問は、授業とは関係のない質問になりますが、教育用資産の有効活用について、おたずねします。市内には小中学校などの教育用資産がたくさんありますが、特に小学校は中学校のようにクラブ活動もないため、放課後や土曜日曜は校門にも鍵がかけられて、まさしく児童や近隣の住民をロックアウトしています。このような状態は、「教育をオープン」という市長のスローガンにもふさわしくありません。校門に鍵をかけることをやめてグランドを開放するだけでなく、体育館やアキ教室などを有料で貸し出すことにも意義があると思います。現に独立法人化された国立大学も施設の積極的な貸し出しを行っています。管理責任や管理コストの問題は、工夫次第で解決できる問題であり、夜間・休日は児童公園として取り扱えば、校長や教員に責任が及ぶこともないと思います。「教育をオープン」というスローガンは、まず学校の施設を市民にオープンにすることから初めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
7.最後にPTAについてお尋ねします。PTAは教育委員会などとともに、戦後の学校教育民主化のため、アメリカの制度に習って日本に導入されたものと言われております。その本来の活動は、保護者と先生が共同して学校をよくしていくことにあると思いますが、ときに先生方の雑用を手伝うようなことまであり、夫婦で働いている家庭にとっては大きな負担になっています。本来PTAは任意加入団体であり、生徒の入学と同時にウムをいわせず加入手続きをさせること、また保護者会でムリヤリ役職を割り当てるようなことはやめるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
以上の私の質問は、日本中の学校でどこでも同じように行われている教育のあり方に異議申し立てをするものであって、宝塚の市議会でそんなことを言っても仕方がないと感じた方も多いと思います。しかし、日本中の学校でどこでも同じように行われていることであっても、実は法律で決まっているわけではなく、習慣として行われてきただけ、あるいは校長や先生に便利で都合がいいからそうやっているだけ、ということが多いといわれます。たとえば最近、東京のある公立中校では、クラス担任制や中間・期末テスト、宿題なども全部やめてしまって、「学校のあたり前をやめた」として大きな話題になりました。全面的に賛成できないにしても、校長一人でも、その気になれば何でもできるという見本だと思います。
そもそも公立の小中学校の学校設置者は市町村であり、それを民主的に管理運営するために教育委員会というものがあるはずです。教育委員会が、そのマチの教育に関することは何でも決める、ということが、本来のあるべき姿です。ところが教育委員会は、今や形だけの存在となっており、その実務を取りしきる事務局は、ひたすら国の言うことだけを聞いてモノごとを決める、国の出先機関のような存在になっているといわれます。例えば昨年2月27日、突如として総理大臣から全国一斉の休校要請が出されましたが、実は総理大臣にそのような権限は何もなく、むしろ各地の教育委員会が、その実情に応じた措置をとらなかったことに大きな問題があるといわれています。
私が述べたことの中でも、特に習熟度別学習や、意欲ある生徒に対する特別授業の提案は、私とは立場の異なる方々から見れば、戦後日本の教育が一貫して追求してきた教育の平等に反するものになると思います。しかし画一的な平等主義こそ、幾多の教育改革の妨げとなり、教育行政の怠慢の隠れ蓑とされてきたものであって、児童・生徒の個性や能力の違いを認めない平等主義は、生徒にとって、せっかくの学校の勉強を、退屈でムダの多いものにしていると思います。これからの教育にもとめられるものは、生徒ひとりひとりが自分の個性や能力を自由に生かすことができる教育であり、教育の平等だけでなく、教育の自由こそもっと尊重されなければならないと思います。このような方向を目指す教育改革が、公教育の場において、もし公教育であるがゆえにできないとすれば、公教育もやがて民営化の道をたどらざるを得ない、と私は思っております。以上で一次質問を終わります。(終わり)
**参考文献**
○教育入門 岩波新書 堀尾輝久
◎教育委員会 岩波新書 新藤宗之
○学校の戦後史 岩波新書 木村 元
○教育改革 岩波新書 藤田英典
○日本の公教育 中公新書 中澤 渉
○教育と平等 中公新書 苅谷剛彦
○教師崩壊 PHP新書 妹尾昌俊
◎教師と学校の失敗学 PHP新書 妹尾昌俊
◎学校弁護士 角川新書 神内 聡
○残念な教員 光文社新書 林 純次
○学校の当たり前をやめた 時事通信社 工藤勇一
○中学教師裏物語 バジリコ 原田祐輔
○公立学校がなくなる 情報センター出版局 高嶋鉄夫・小篠弘志
○教師の仕事がブラック化する本当の理由 草思社 喜入 克