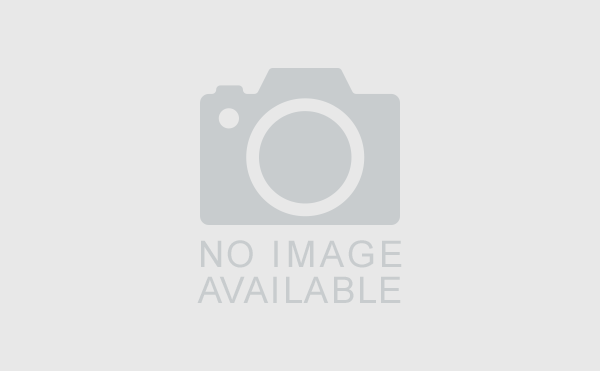宝塚の教育委員会
9月の一般質問では教育について質問しようと思っており(出番は9月29日のトリ)、事前準備として教育委員会事務局に質問状を提出したところ、学校教育部長ほか最高幹部から口頭で説明を受けることができた。
私の質問の主な内容は、1.小中学生の通塾率、私立中学への進学率はどれくらいか。2.公立中学生の学力向上策として、習熟度別の学級編成や放課後の補習は可能か。3.学級崩壊が発生したときや指導力不足教員に対してどのような対応をしているか。4.学校の教室やグラウンドなどを地域の住民に解放したり、民間業者に有償で利用させたりできないかetcである。
予想通り、先方の解答は「教育の平等」を盾にとり、解答拒否的もしくは消極的・否定的な内容に終始した。その背後にあるのは、教育行政の担当者として、自分たちの今までやってきたことは変えたくない、否定されたくないという頑迷な姿勢である。教育委員会とは、本来教育を民主化するためにできた組織であるが、実務を取り仕切っているのは「事務局」であり、その性格は、文部省を頂点とする教育行政機構の地方出先機関のようなものと指摘される。まさにその通りだと実感した。
それともう1つ、予想通りだったことは、いわゆる学習塾を敵視し、私立の中高一貫校などの存在を無視しようとする姿勢である。通塾率について質問したとき、「そういう家庭のプライバシーに関わることは一切調査できない」と言われたが、先生が生徒の家庭環境や学習環境などを全然知らずに、一体どんな教育・授業ができるというのか。自分たちの行っている教育は「公教育」であって、あくまでも文部省の定めた「学習指導要領」に従って進めるというが、今や日本の教育は、「公教育」以外の教育に大きく依存している。「公教育」の関係者が妙なプライドを捨てない限り、日本の教育に未来はないと思う。
補足:私立の中高一貫校も一応公教育であるが、教育委員会による監督もないに等しく、学習指導要領も無視しているので、公教育のイメージからははずれると思う。